2023/10/18 名古屋市千種区史跡散策路 古井の里と丸山村めぐり。 《10月活動紹介》
2023/10/18 名古屋市千種区史跡散策路 古井の里と丸山村めぐり 《10月活動紹介》
✿光正院 (こうしょういん)
永正16(1519)年の創建。本尊は釈迦如来像。
説明版
「尾張志」によれば、永正十年(1513)僧来鳳の創建といわれ、釈迦仏を本尊として安置する。
昔、弁慶が当寺に居住して、手掘りで井戸を掘り、その清水で主君義経の武運を祈願し、大般若経五十卷を書写したと伝える。(市/説明板より)
北門神門
山門

本堂
鐘楼
弘法堂
✿高牟神社 (たかむじんじゃ)
延喜式(927年)にも記載されている古い神社です。尾張物部氏の武器庫が神社になったと伝えられる。
境内には元古井、古井ノ坂といった地名の由来の元となった古井戸がある。
鳥居 石標
東鳥居
西鳥居
拝殿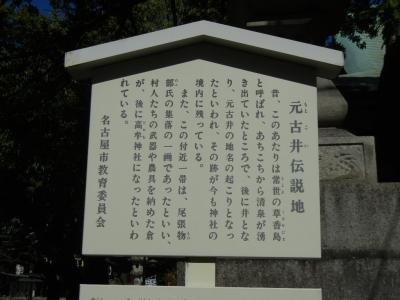
説明版

番塀

北野天満宮 高牟龍神社
〇元古井伝説
このあたりは「常世の草香島」(とこよのくさかじま)と呼ばれ、あちこちから清泉が湧き出ていたところで、後に井となり、元古井の地名の起こりとなったといわれ、その跡が今も神社の境内に残っている。(市/説明板より)
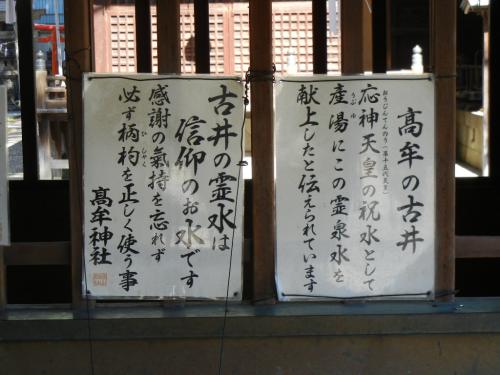
元古井発祥之地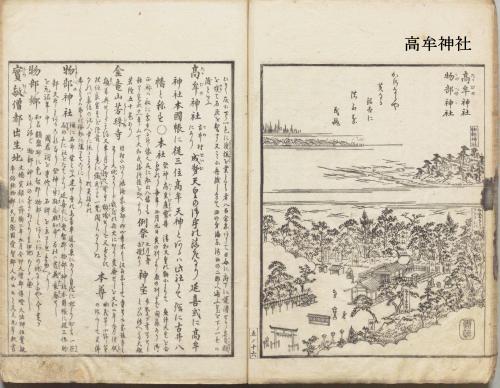
尾張名所図会前五ノ16 高牟神社
✿善久寺 (ぜんきゅうじ)
天正19(1591)年の創建で本尊は聖観世音菩薩です。境内に明治の小作争議の指導者小塚鉞助の碑が建っている。
山門
本堂
善久寺秋葉堂
小塚鉞助招魂碑と六地蔵
✿光専寺 (こうせんじ)
文禄二年(1593)加藤清正の弟兵部少輔祐正が創建した。当時はこの辺りから丸山村にかけて、多くの信徒を持った。
山門
本堂
✿芳珠寺 (ほうしゅうじ)
本尊は延命地蔵菩薩。南北朝から室町時代の作で秘仏。尾張六地蔵の第六番札所です。
山門
本堂
延命地蔵菩薩
弘法堂
《》尾張六地蔵霊場《》
1番は長光寺(汗かき地蔵)、2番は清浄寺(矢場地蔵)、3番は地蔵院(湯谷地蔵)
4番は如意寺(せき地蔵)、5番は島田地蔵寺(毛替地蔵)、6番は芳珠寺(延命地蔵)です。
✿今池地蔵
かつてこの辺りにあった馬池で溺れた人の供養のために、明治の終わり頃に建立された地蔵尊です。

地蔵尊
✿吹上八幡社
安政五年(1857)御器所村で創建され、明治十九年(1886)に現在地に移る。
山門 石標
拝殿
御神木への参道
✿吹上観音(ふきあげかんのん)白龍大神
石造の千手観音像です。
名古屋新田の開拓は万治年間(1658~1660)新田頭小塚源兵衛が務めた。
入口 刻字は「小塚氏名古屋新田開墾記念碑」
拝殿
白龍大神
✿法応寺 ほうおうじ
天正十五年(1589)清洲に創建。清洲越えを経て、現在地に移転する。境内には、芭蕉門下の月空庵露川の「丸屋こそよけれ 四角な冬ごもり」の句碑がある。
山門
本堂
月空庵の碑 刻字は「丸屋こそよけれ 四角な冬ごもり」
✿法蔵寺

山門

山門の扉
本堂
✿塩付街道・馬頭観音(しおつけかいどう)
塩付街道は、かつて南区の星崎辺りの浜で作られた塩を、内陸へ運ぶ道として利用されたところから、そう呼ばれた。

馬頭観音
✿光明寺 (こうみょうじ)
名古屋城築城の際に勘定方役人であった、鈴木安太夫重政の墓があり、寛文十一年(1671)没した。重政は、この地から築城のための用材を切り出し、跡地を田畑にしたといわれている。
入口
石標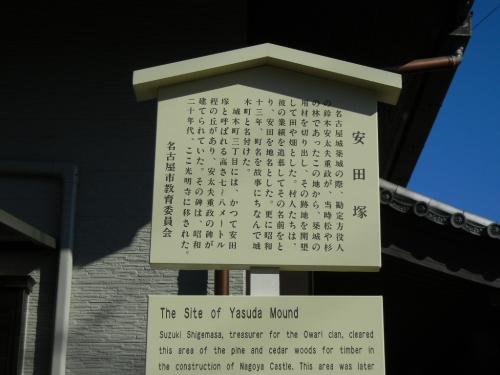
説明版 安田塚
本堂
石碑 刻字は「俗名鈴木安太郎夫重政」
✿松林寺 (しょうりんじ)
元亀二年(1571)の創建。本尊は薬師瑠璃光如来。両側に日光、月光菩薩、他に毘沙門天が祀ってある。
山門
本堂
✿丸山神明社(まるやましんめいしゃ)
16世紀後半の建立という。入り口左手には、天保五年(1834)「村中安全」と彫られた、区内では数少ない秋葉常夜灯がある。
鳥居 石標
石標 秋葉常夜燈
拝殿
✿一畑山薬師寺名古屋別院(いちはたさんやくしじ)
臨済宗の寺で本尊は薬師如来であり、現世、未来ともに救われる仏様といわれている。
山門と本堂1348
境内
以上
この情報は、「歴史探訪街道ウォーキングの会」により登録されました。